-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
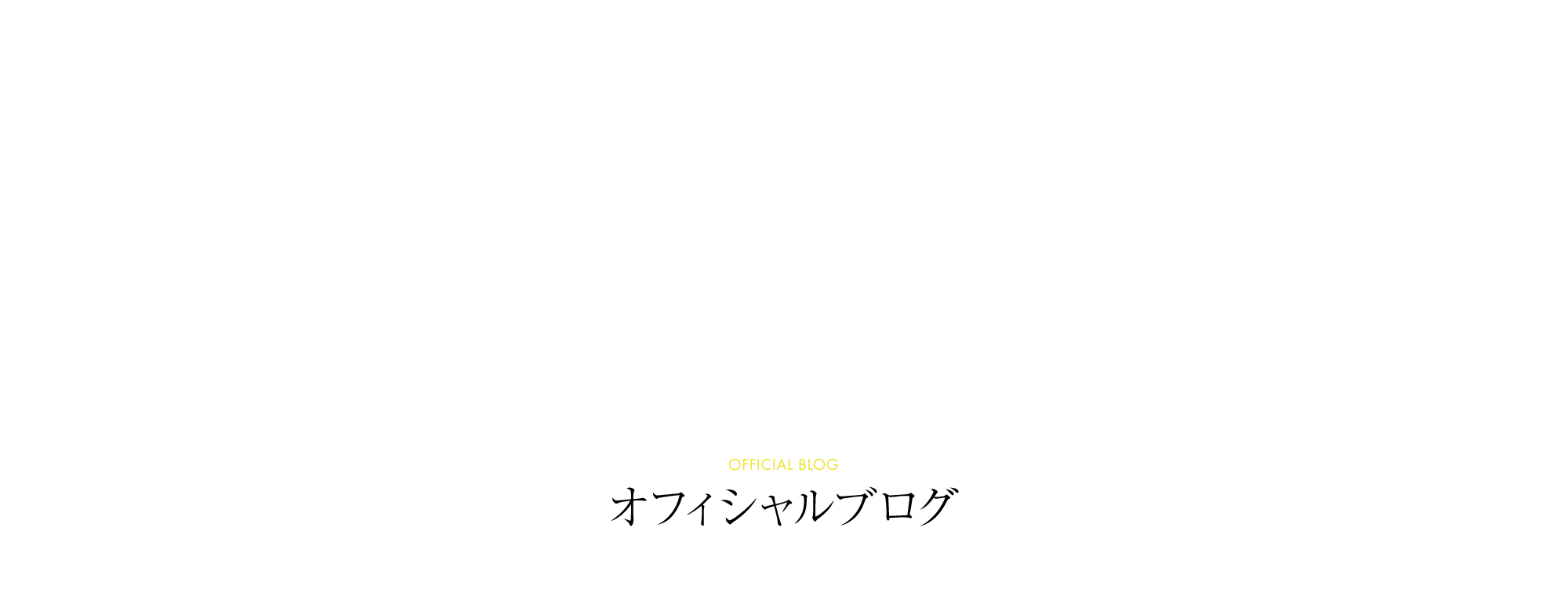
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の那須です。
本日は「建築メンテナンス講座」として、 「住まいを長持ちさせるための年間メンテナンススケジュール」についてお届けします。
建物は定期的な手入れを行うことで、寿命を延ばすことができます。とはいえ、どの時期に何をすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか?
今回は、季節ごとに行うべきメンテナンスポイントを整理してご紹介します。
季節ごとに行うべきメンテナンスを習慣にすることで、住まいの寿命を延ばし、快適な生活を保つことができます。
次回は「DIYでできる簡単メンテナンス」についてお届けする予定です。ご家庭で手軽にできる補修や掃除のテクニックをご紹介しますので、お楽しみに!
株式会社龍栄では、建築メンテナンスや防水工事に関するスタッフを随時募集中です。 未経験の方も歓迎です。お気軽に求人ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の那須です。
本日は「建築メンテナンス講座」として、 「床下の湿気対策と換気の重要性」についてお届けします。
床下に湿気がたまると、次のような問題が発生します:
床下の湿気は、ただ不快なだけではなく、建物の寿命を左右する大きな要因となります。
【換気口の確保と点検】
【床下換気扇の設置】
【防湿シートの敷設】
【床下調湿材の利用】
床下は普段見えないからこそ、定期的な点検が非常に重要です。
点検時のチェックポイント:
床下の湿気対策は、プロの施工に加えて日常の習慣でも予防が可能です。
こうした日々の積み重ねが、建物の健康寿命を延ばすことに直結します。
次回は「住まいを長持ちさせるための年間メンテナンススケジュール」をご紹介します。 1年を通してどの時期にどんな点検や補修を行うべきか、管理のポイントを詳しくお届けする予定です。
株式会社龍栄では、建築メンテナンスや防水工事に興味のある方を随時募集中です。 未経験の方でも安心してスタートできるよう、丁寧な研修制度と現場サポート体制をご用意しています。
詳しくは求人ページをご確認ください。 皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の那須です。
本日は「建築メンテナンス講座」第6回として、「建物の基礎部分の点検と補修」についてお届けします。
建物の基礎は、構造全体を支える非常に重要な部分です。目に見える場所ではないため、普段はあまり意識されませんが、ひび割れや沈下などのトラブルが起きると、建物全体に影響を及ぼす恐れがあります。長く安全に暮らすためにも、基礎部分の定期的な点検と適切な補修が欠かせません。
◆ 基礎の劣化がもたらす影響 建物の基礎部分が劣化すると、以下のような症状が現れることがあります。
これらはすべて、基礎部分の沈下やひび割れ、水の浸入などが原因で起こることが多いです。早期の対応が重要です。
◆ 基礎の主なトラブルと対策
【ひび割れ(クラック)】 乾燥収縮や地盤の動きなどにより発生。幅0.3mm以上のひび割れは構造上の問題となる可能性があるため、補修が必要です。
【不同沈下】 地盤が不均等に沈むことで建物が傾く現象。軽度であれば調整可能ですが、重度の場合は地盤改良などの大規模工事が必要になることもあります。
【防水性の低下】 基礎に水が染み込みやすくなると、内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートを破壊する恐れがあります。止水材の注入や外側からの防水塗装などで対応可能です。
◆ 点検のポイント 基礎部分の点検は、以下のようなポイントを押さえて行いましょう。
定期的な点検により、早期発見・早期対応が可能になります。特に築10年以上経過した建物では、年に1回の目視点検をおすすめします。
◆ 補修方法について 軽度のクラックであれば、エポキシ樹脂やセメント系材料を用いた注入工法で補修できます。 深刻な場合は、外周部の掘削、防水層の再施工、地盤改良工事などが必要となることもあります。専門業者による診断と施工が不可欠です。
次回は「床下の湿気対策と換気の重要性」についてお届けします。基礎と並んで建物を支える床下環境にも、快適な住まいを守るための工夫が必要です。どうぞお楽しみに!
株式会社龍栄では、建築メンテナンスや防水工事に関わるスタッフを募集中です。 経験・未経験問わず、熱意のある方を歓迎します!
詳しくは求人ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の那須です。
本日は「建築メンテナンス講座」第5回として、「ベランダやバルコニーの防水メンテナンス」についてお届けします。
ベランダやバルコニーは、日常的に使うスペースでありながら、屋外に面しているため風雨や紫外線の影響を大きく受ける場所です。ここが劣化すると雨漏りや建物内部への浸水といった深刻なトラブルに繋がる恐れがあります。だからこそ、定期的な防水メンテナンスが非常に重要なのです。
◆ なぜ防水が必要なのか? ベランダやバルコニーの床面には、防水層と呼ばれる水を通さない膜が施工されています。この防水層があることで、雨水が建物内部に浸入するのを防いでいます。しかし、経年劣化により防水層が傷んでくると、亀裂や浮き、剥がれが発生し、水漏れの原因になります。
特に、ベランダの下に部屋がある構造の住宅では、水漏れが天井から発生し、クロスのシミやカビ、場合によっては電気系統への悪影響を及ぼすこともあります。
◆ 劣化のサインを見逃さない 以下のような症状が見られたら、防水層の劣化が進んでいる可能性があります。
これらを放置しておくと、雨漏りだけでなく構造材の腐食など、修繕費用の高額化にも繋がってしまいます。
◆ 防水工事の種類と特徴
【ウレタン防水】 液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を作る工法で、複雑な形状にも対応可能。費用も比較的安価で人気があります。
【FRP防水】 ガラス繊維を混ぜた樹脂で防水層を形成する方法で、硬化後は非常に頑丈。耐摩耗性に優れ、戸建て住宅のバルコニーなどによく使われます。
【シート防水】 塩ビシートやゴムシートを接着する工法で、施工が比較的早く済みますが、下地の状態によっては不向きな場合もあります。
◆ 定期的な点検・メンテナンスが鍵 防水層の耐用年数は10〜15年程度とされていますが、使用環境によって差があります。施工後5年目を目安に、一度専門業者に点検してもらうことをおすすめします。
点検では、防水層の状態や排水口の機能、ひび割れの有無、下地の状況などをチェックし、必要に応じて補修や再施工を行います。
◆ 日常のケアも大切です
これらのちょっとした心がけで、防水層への負担を減らし、寿命を延ばすことができます。
次回は「建物の基礎部分の点検と補修」について解説予定です。目に見えにくい部分だからこそ、見逃せないポイントをお伝えします。ぜひお楽しみに!
株式会社龍栄では、防水工事や建築メンテナンスに興味のある方を募集中です。 未経験の方も大歓迎!現場で学びながら確かなスキルを身につけていただけます。 詳しくは求人ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の岡です。
本日は「建築メンテナンス講座」第4回として、「外壁塗装の必要性とタイミング」についてお届けします。 建物の見た目を美しく保つだけでなく、建物自体を長く守るためにも外壁塗装は欠かせません。
外壁塗装には、見た目の美しさを保つ「美観」の役割と、風雨や紫外線などの自然環境から建物を守る「保護」の役割があります。 これらの機能がきちんと果たされていないと、外壁が劣化し、最終的には建物全体の寿命を縮めてしまうことにもなります。
◆ 外壁塗装が必要な理由
【防水性の確保】
外壁の塗膜には、雨水をはじき外壁内部に浸透させないという大切な役割があります。塗膜が劣化すると、雨水が染み込みやすくなり、外壁内部の断熱材や構造体にまで影響を与える恐れがあります。結果的に、雨漏りや腐食、カビの発生など深刻なトラブルに繋がることも。
【紫外線や気温変化への対策】
外壁は毎日、強い紫外線や激しい寒暖差にさらされています。これらの影響で塗膜は少しずつ劣化し、ひび割れ、変色、チョーキング(白い粉が出る現象)などが現れます。塗装によって、こうした自然のダメージから建物を守ることができます。
【美観の維持】
時間とともに塗装の色はあせ、外壁にはホコリや雨だれ、カビや苔などの汚れが付着していきます。外壁塗装を定期的に行うことで、建物の美しさを取り戻すとともに、街並みや周囲の環境に調和した外観を維持できます。
◆ 塗り替えのタイミングは?
外壁塗装のタイミングは、建物の構造、立地環境、使用されている塗料の種類によって異なりますが、一般的には10年前後が目安とされています。以下のような症状が見られたら、塗り替えを検討しましょう。
・外壁に小さなひび割れ(ヘアクラック)がある
・手で壁を触ると白い粉がつく(チョーキング現象)
・カビや苔、藻が広がっている
・塗膜の剥がれや膨れが見られる
・外壁の色が明らかに褪せてきている
これらのサインを放置していると、塗膜の機能が失われて建物内部に水が入り込み、建物全体の劣化が急速に進行することになります。
◆ 塗装工事を成功させるためのポイント
塗装工事は見た目を綺麗にするだけでなく、建物の寿命を延ばすための重要な工事です。そのため、以下のポイントに注意して進めることが大切です。
・信頼できる業者を選ぶ: 実績や資格、施工事例、保証体制などをしっかり確認しましょう。適正な見積もりを提示し、疑問にも丁寧に答えてくれる業者が理想的です。
・塗料の種類と性能を把握する: 使用される塗料にはアクリル、ウレタン、シリコン、フッ素などの種類があり、それぞれ耐久性や価格が異なります。建物の条件や予算に応じて最適なものを選びましょう。
・工事前の打ち合わせを大切に: 色決めや工程の確認、近隣へのあいさつや足場の設置など、細かい部分までしっかり話し合っておくことで、安心して施工を任せられます。
外壁塗装は、定期的に行うことで建物の寿命を延ばし、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。特に築10年以上経過している建物は、一度専門業者に診断を依頼してみるとよいでしょう。無料診断を実施している業者も多いので、まずは気軽に相談してみてください。
次回は「ベランダやバルコニーの防水メンテナンス」について解説します。 屋外で風雨にさらされるこれらのスペースも、定期的な防水チェックが必要不可欠です。 快適な住まいを維持するために知っておきたいポイントをお届けしますので、ぜひご覧ください!
株式会社龍栄では、防水工事や建築メンテナンスに興味をお持ちの方を募集しています。 未経験でも大歓迎!丁寧な研修とサポート体制で、安心してスタートできます。
詳しくは求人ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の岡です。
今回の「建築メンテナンス講座」第3回では、「雨漏りの原因と対策」についてお届けします。 雨漏りは、建物の安全性や快適性を大きく損なう問題であり、早期発見と正しい対策が非常に重要です。
雨漏りは一見すると小さなトラブルのように見えますが、放置すると構造部分の腐食やカビの発生、電気設備への影響など、住まいや生活に大きな被害を及ぼす可能性があります。この記事では、よくある雨漏りの原因とその対策、そして日常的にできる予防法について詳しく解説します。
◆ 雨漏りが起こる主な原因
【屋根の劣化・破損】
・屋根は風雨や紫外線にさらされており、最も劣化が進みやすい箇所の一つです。
・屋根材のひび割れ、ズレ、破損によって雨水が侵入しやすくなります。
・特に台風や強風の後は、屋根の状態を自分で確認するか、業者に依頼して点検することをおすすめします。
【外壁のひび割れ】
・モルタルやコンクリートの外壁にできた小さなひびからでも、雨水は浸入してしまいます。
・ひび割れが進行すると、外壁の内部にまで浸水し、建物の基礎部分にまで影響を与えることがあります。
・放置せず、小さな亀裂も見逃さず早期に補修することが大切です。
【シーリング材の劣化】
・窓枠や外壁の目地に使われるシーリング材は、紫外線や経年劣化によりひび割れや剥離
が生じます。
・劣化が進むと、隙間から水が入り込むようになり、雨漏りの原因となります。
・おおよそ10年前後で打ち替えが必要になるため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。
【ベランダ・バルコニーの防水不良】
・ベランダやバルコニーの防水層が劣化していたり、排水口が詰まっていたりすると、水たまりが発生しやすくなります。
・そこから水が建物内部に浸透し、階下への漏水トラブルになることもあります。
・定期的に清掃を行い、防水層の再施工時期を見極めることが重要です。
◆ 雨漏りの対策と予防法
・定期点検の実施: 屋根、外壁、ベランダなどの点検を年1〜2回の頻度で実施し、ひび割れや劣化を早期に発見しましょう。
・早めの補修工事: 小さなトラブルでも放置せず、発見したらすぐに補修することが被害の拡大を防ぐポイントです。
・防水工事の再施工: 防水層の耐用年数(約10〜15年)を過ぎている場合は、全面的な再施工を検討する必要があります。 特に古い建物では、下地からの劣化も考慮して丁寧な診断が必要です。
・専門業者への相談: 状況の判断が難しい場合や、高所の点検が必要な場合は、信頼できる専門業者に依頼するのが最も安心・確実です。
また、雨漏りが発生した際には応急処置だけで済ませず、根本原因をしっかり調査して恒久的な対策を取ることが、再発防止につながります。
雨漏りは建物の寿命を左右する重要な問題です。日頃の点検と早めの対応が、住まいの資産価値を守り、快適な生活環境を維持するカギとなります。
次回は「外壁塗装の必要性とタイミング」についてお届けします。 建物の美観を保つだけでなく、耐久性を向上させるためにも大切な外壁塗装の役割を、わかりやすくご紹介します。ぜひお楽しみに!
株式会社龍栄では、防水工事や建築メンテナンスに興味のある新しい仲間を募集中です。 未経験の方も大歓迎!経験豊富なスタッフが丁寧にサポートします。
詳細は求人ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の岡です!
前回の講座では、建物の寿命を延ばすための基本メンテナンスについてお話ししました。今回は「防水対策の重要性と効果的な方法」についてご紹介します!
建物における防水は、外壁や屋根、ベランダなどのあらゆる部分で必要とされる重要な施工です。適切な防水工事を施すことで、雨水の侵入を防ぎ、内部の構造を守ることができます。しかし、施工が不十分だったり、経年劣化によって防水層が機能しなくなると、雨漏りや建物の腐食が進行し、大規模な修繕が必要になってしまいます。
◆ 防水工事の種類と特徴
【ウレタン防水】
・液状のウレタン樹脂を塗布し、固まるとゴムのような弾力のある防水層を形成。
・施工性が高く、複雑な形状の場所にも適用可能。
・耐用年数は約10~15年。
【シート防水】
・塩ビシートやゴムシートを敷き詰めて防水層を形成。
・耐久性が高く、屋上やベランダなど広い面積に適している。
・シートの接着面から雨水が浸入するリスクがあるため、確実な施工が必要。
【FRP防水】
・ガラス繊維強化プラスチックを使用し、硬く丈夫な防水層を作る。
・高い耐摩耗性と耐久性があり、ベランダなど狭い範囲に適している。
【アスファルト防水】
・アスファルトシートを重ねて敷き詰める工法。
・耐久性が非常に高く、大規模な建物の屋上に多く採用
・施工には専門技術が必要で、工期が長くなることもある。
◆ 防水工事のメンテナンス
・定期点検:防水層のひび割れや剥がれを早期に発見し、補修することでトラブルを防ぐ。
・清掃:ゴミや汚れが防水層を劣化させる原因になるため、定期的に清掃を行う。
・再施工:防水工事は耐用年数があるため、劣化が進んだら早めの再施工を検討する。
防水対策を怠ると、建物の耐久性が低下し、結果的に修繕費用が高額になることがあります。適切な防水工事を行い、定期的に点検・メンテナンスをすることで、長く快適な住環境を維持することができます。
次回は「雨漏りの原因と対策」についてお届けします。雨漏りの原因を知り、適切な対応方法を学ぶことで、被害を最小限に抑えることができます。ぜひお楽しみに!
株式会社龍栄では、一緒に働いてくださる仲間を募集しています。防水工事に興味のある方、未経験の方も大歓迎です。経験豊富なスタッフがサポートしますので、安心してご応募ください。詳細は求人ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の岡です!
新シリーズ「建築メンテナンス講座」をスタートします! 建物を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。 このシリーズでは、建築物の維持管理に役立つ情報をお届けします。
目次
建物は時間とともに劣化していきますが、適切なメンテナンスを行うことで寿命を大幅に延ばすことができます。 ここでは、基本的なメンテナンスのポイントをご紹介します。
・ひび割れがないか定期的にチェックし、早めに補修を行いましょう。
・防水塗装を施すことで、耐久性を向上させることができます。
・ひび割れが進行すると雨水が侵入し、内部の鉄筋を腐食させる原因になるため、放置せずに対処することが大切です。
・外壁の汚れやカビの発生も、劣化のサインとなることがあります。定期的な洗浄も重要です。
・雨漏りを防ぐため、瓦やシートのずれがないか確認しましょう。
・特に台風や豪雨の後は入念にチェックを行い、必要ならば専門業者に相談を。
・屋根の劣化が進むと、断熱性が低下し、夏場の室内温度上昇や冬場の冷え込みの原因になります。定期的な点検と補修を心がけましょう。
・屋根に苔や藻が発生している場合、それが劣化のサインであることが多いため、早めにクリーニングを行いましょう。
・配管の詰まりや水漏れがないか定期的に点検。
・水道管の老朽化を防ぐために、適宜メンテナンスを行いましょう。
・特に冬場は水道管の凍結に注意し、適切な断熱処理を施しておくことが重要です。
・水の流れが悪くなった場合は、排水管の詰まりが原因であることが多いため、早めに対処しましょう。
・換気を十分に行い、カビや湿気対策を徹底しましょう。
・床や壁の損傷があれば、早めに補修することで劣化を防げます。
・特に湿気の多い場所では、防カビ剤を使用し、定期的に掃除を行うことが推奨されます。
・窓やサッシの隙間から風が入る場合は、断熱シールなどを使用して隙間をふさぎ、エネルギー効率を向上させましょう。
・コンセントや配線の焦げ跡や異常な熱を確認し、火災のリスクを防ぎましょう。
・古くなったブレーカーや電気設備は早めに交換し、安全性を確保することが大切です。
・省エネ対策として、LED照明の導入なども検討すると良いでしょう。
・電気の使用量を抑えるため、不要な電化製品の待機電力をカットすることも推奨されます。
建物を長持ちさせるためには、日々の点検と適切なメンテナンスが不可欠です。 少しの手間で、大きな修繕を防ぐことができますので、ぜひ実践してみてください。
次回は「防水対策の重要性と効果的な方法」についてお届けします。お楽しみに!
建築メンテナンスや防水工事に興味のある方、未経験でも大歓迎です!
経験豊富なスタッフがサポートしますので、安心してご応募ください!
詳細は求人ページをご覧ください。 皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の那須です。
寒波が続き、寒さが厳しくなる季節ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
防水工事は年間を通して重要な施工ですが、特に冬場は凍結や気温の影響を考慮する必要があります。
さて、本日は第7回防水工事雑学講座をお届けします! 今回のテーマは、「防水工事における冬場の注意点」についてです。
冬場の防水工事における注意点
防水工事は気温や湿度の影響を受けやすく、施工時期によって適切な対応が求められます。 冬場に施工する際の注意点をいくつかご紹介します。
①材料の取り扱いに注意
冬場の低温環境では、防水材の粘度が高くなり、施工が難しくなることがあります。 そのため、材料の保管温度を適切に管理し、施工前に十分に温めることが重要です。
②乾燥時間の確保
気温が低いと防水材の硬化・乾燥に時間がかかるため、通常よりも長い乾燥時間を確保する必要があります。 急いで次の工程に進めてしまうと、施工不良の原因となるため注意が必要です。
③凍結による影響を防ぐ
施工面に霜や氷が付着していると、防水材がしっかりと密着しません。 施工前には十分に清掃し、表面を乾燥させることが大切です。
④気温に適した防水工法の選択
低温環境でも施工が可能な防水工法を選ぶことも、冬場の防水工事成功のカギです。 ウレタン防水やシート防水など、それぞれの特性を理解し、適切な工法を選びましょう。
まとめ
冬場の防水工事は、気温や乾燥時間を考慮しながら慎重に進めることが重要です。 適切な材料の取り扱いと環境管理を徹底し、確実な施工を行いましょう。
次回の防水工事雑学講座では、「防水工事における最新技術と今後の展望」についてご紹介します。 お楽しみに!
防水工事に興味のある方、一緒に働きませんか? 未経験の方も大歓迎!経験豊富なスタッフがしっかりサポートします。
私たちが大切にしているのは「人柄」です。 風通しの良い職場で、チームワークを大切にしながら成長していきましょう。
詳細は求人ページをご覧ください。 皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
皆さんこんにちは! 株式会社龍栄、更新担当の那須です。
2025年が始まり、すでに2ヶ月が過ぎましたが、昨年も多くのお客様に支えられ、無事に1年を終えることができました。本当にありがとうございました!
さて、去年の出来事なのですが、弊社では2024年の忘年会を開催しました!
今年の忘年会は、社員一同が集まり、1年間の頑張りを称え合う楽しい時間となりました!

おいしい料理を囲みながら、日頃の疲れを癒しつつ、さまざまな話題で盛り上がりました!
2025年も、より一層の成長を目指し、チーム一丸となって頑張っていきます!
私たち株式会社龍栄では、一緒に働いてくださる方を募集しています。
特に未経験の方でも、やる気と意欲があれば大歓迎!経験豊富な先輩スタッフがしっかりサポートしますので、安心してご応募ください。
私たちが大切にしているのは「人柄」です。 風通しの良い職場で、チームワークを大切にしながら、一緒に成長していきませんか?
詳細は求人ページをご覧ください! 皆さまのご応募を心よりお待ちしております!